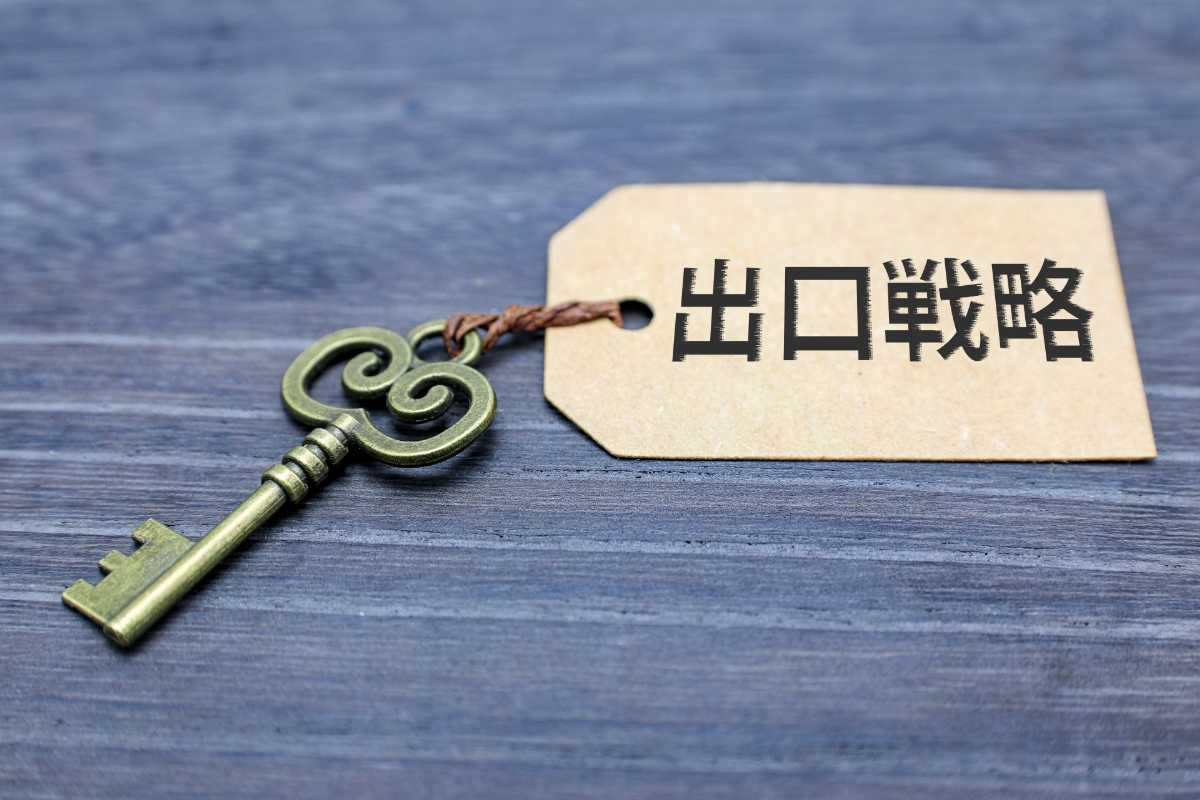不動産投資の成功に大きく関わってくる出口戦略。
出口戦略とは、投資の最終地点を考えることで不動産投資における出口戦略は「売却方法を考えること」といえます。
この「売却戦略」を立てておかなければ、収益性の低い物件でも保有し続けるしかなく、損失を生み続ける可能性があるのです。
そうならないために、不動産投資を検討している方はまず「出口戦略」について学ぶ必要があります。
本記事では、手元資金100万円から2022年には純資産20億円を突破した小原正徳が、具体例も交えながら不動産投資の出口戦略について解説していきます。
”元ゴールドマン・サックス不動産投資家が教える失敗しない不動産投資の成功法則”を
LINE友だち限定でお伝えします。
LINE登録でもらえる豪華6大特典
①数字とエビデンスに基づく投資判断マニュアル
②自分に最適な「融資」を見つけるガイド
③不動産購入前に必ず確認すべき「リスク」と「資料」
④ 「お宝物件」発掘のための効果的な探し方
⑤『不動産購入「現地調査」で確認すべきチェックリスト
⑥不動産運営にかかる収益費用の把握の仕方
LINE友だち追加してくれた方だけに、登録者6万人のYouTubeでも話せない情報をお届けしています
小原正徳の公式LINEはこちらから
▼スマホはこちらから限定情報をGET!▼
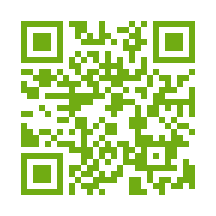

【監修者情報】不動産投資家 小原 正徳
1981年4月6日生まれ 不動産投資家
東京大学卒業後、EYグループ不動産部門、
ゴールドマン・サックスグループ不動産ファンド部門を経て
2016年に東京都新宿区株式会社不動産科学研究所で独立
2022年には総資産20億円を形成
同年、新たなチャレンジとして不動産投資スクールを開校し、自身の培ったノウハウの提供を開始
株式会社不動産科学研究所 代表取締役
宅地建物取引士
不動産鑑定士
不動産証券化協会認定マスター
不動産投資の「出口戦略」とは?|売却だけじゃないその本質

不動産投資における「出口戦略」とは、投資した物件を最終的にどう処分するかという計画全般を指します。
出口戦略を疎かにすると、運用中に得た利益が0になってしまうほど、不動産投資の中では影響力が大きいものです。
つまり、どれだけ家賃収入で利益を得ていても、出口で失敗すれば最終的に損失に転じてしまう可能性があるのです。
投資用物件は自宅と異なり、いつか何らかの形で手放すことを前提にしています。購入時より高い価格で売却できて初めて、手数料や金利を差し引いた正味の利益が確定します。
したがって運用期間中のインカムゲイン(家賃収入)だけでなく、最終的にどうキャピタルゲイン(売却益)を得るかまで考える必要があります。出口戦略とは、「どのタイミングで」「どんな方法で」「いくらで」物件を手放すかというシナリオを事前に描くことにほかなりません。
売却だけが選択肢ではなく、後述するように借り換えや大規模修繕による継続保有など複数のルートがあります。
出口戦略の定義と3つの代表パターン
出口戦略の狭義には「物件を売却して投資を終了すること」を指しますが、それだけではありません。
不動産投資の出口戦略として代表的な3パターンは、以下のとおりです。
「売却」「借り換え(リファイナンス)」「大規模修繕による継続保有」の3パターンについて解説します。
| 出口戦略の種類 | 概要・特徴 | メリット | 注意点・デメリット |
|---|---|---|---|
| 売却 | 物件を売って現金化する基本的な方法。空室売却と入居中売却の選択がある。 |
|
|
| 借り換え(リファイナンス) | 融資条件を見直し、金利負担を軽減または追加融資で資金調達を図る。 |
|
|
| 大規模修繕と継続保有 | 築年に応じた修繕で物件価値を維持し、長期保有を前提とする戦略。 |
|
|
売却戦略は文字通り物件を売り現金化する方法で、最もオーソドックスな出口です。
借り換え戦略は現在の融資を別の融資に組み替えることで金利や月々の負担を減らしたり、追加資金を得たりして投資の続きを有利に進める手法です。
大規模修繕による継続保有は、物件の老朽化に合わせて大きな修繕投資を行い物件価値を維持・向上させることで、売却を先延ばしする戦略と位置付けられます。
出口戦略というと売却だけが注目されがちですが、実際には融資の組み直しや物件の改善も含め、広い意味で「出口」をデザインすることができるのです。
不動産投資で出口戦略を考える必要性
不動産投資では、「購入する前」にすでに出口戦略を考えておくことが不可欠です。
購入後に思いつきで売却プランを練っても遅く、物件を買う段階で出口を想定しておかなければならないと言われます。これは、購入時にほとんど勝負が決まってしまうからです。
価格や収支構造、将来の選択肢は実はすべて購入時点である程度決まっており、買った後では変えられない要素が多いのです。
物件の立地や構造、そして購入価格やローン条件といったものは、一度買ってしまうと後から変更するのが極めて難しくなります。
例えば物件の所在地や築年数は変えられませんし、借入条件も契約後に大きく緩和されることは通常ありません。
そのため、購入前から「この物件は将来どのくらいで、どうやって売れそうか」を検討しておく必要があるのです。購入時に出口まで見据えた判断をしなければ、後で「こんなはずじゃなかった」と後悔するリスクが高まるのです。
逆に言えば、出口を意識して物件選び・資金計画を行えば、投資の最後で失敗する危険性を極限まで減らせます。
不動産投資は「出口戦略=入口戦略」と言われます。最初にどんな物件をどんな条件で買うかが、最後にどのように投資を終わらせられるかが決まるのです。
したがって、購入前から複数の出口シナリオを描き、それでもリスクに耐えられる物件かを見極めることが肝心です。
出口戦略の選択肢|目的に応じて柔軟に使い分ける

出口戦略には複数の選択肢があり、投資家の目的や資産状況に応じて最適解は異なります。
大きく分ければ「物件を手放すか保有し続けるか」「現金を回収するか資金調達するか」といった視点で整理できます。
例えば、できるだけ早くキャッシュを回収して別の資産に乗り換えたいなら売却戦略を選びます。
一方で、物件を持ち続けて安定収入を得ながら資金繰りを改善したいなら借り換え戦略を選びましょう。
長期保有を前提に資産価値を維持したいなら大規模修繕戦略を選ぶ、という具合に、自分の投資目的(守り重視か攻め重視か)によって出口の取り方を柔軟に変えることが大切です。
ここからは、それぞれの戦略を具体例を交えながら解説していきます。
売却戦略|キャッシュ回収と資産入れ替えの王道
売却による出口戦略は、不動産投資で最もオーソドックスかつ王道と言える手法です。
物件を売却することで、それまで不動産に固定されていた資産を現金化し、ローンの残債を精算して手元にキャッシュを回収できます。
これにより、新たな物件への乗り換え(資産の入れ替え)も容易になり、投資ポートフォリオを効率的に拡大・刷新することが可能です。
含み益が出ている物件であれば、そのキャピタルゲインを実現化する絶好の機会になります。
売却戦略を成功させるポイントは、市場価格・タイミング・残債の3つを見極めることです。
まず市場価格については、不動産市況が好調な局面や物件エリアの需要が高まっている時期を狙うことで、高値で売却しやすくなります。
特に近年は、物件保有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり税率が約20%に下がる(5年以下だと約39%)という税制もあるため、税負担の軽くなる5年超のタイミングを一つの目安にする投資家も多いです。
売却戦略の具体例
例えば一棟アパートを5年前に1億円で購入し、ローン残高が8000万円残っているケースを考えます。
市場の家賃相場上昇と物件の運営改善により、現在の売却相場は1億2000万円程度と試算されました。
この場合、売却すれば残債を差し引いても約4000万円のプラスが見込めます。
さらに個人の場合は、所有期間5年を超えていれば譲渡税も長期譲渡扱いで約20%に抑えられます。そこでオーナーは長期譲渡に切り替わる6年目に売却することを決断しました。
その結果、ローンを完済して手元に数千万円のキャッシュが残り、それを元手に別の有望な物件へ買い換えることができました。
建物が老朽化して修繕費用が嵩むようなら、解体して土地として売り出すことで買い手の利用自由度が上がり、早く高く売れる可能性が高まるからです。
このように売却戦略にはさまざまな応用がありますが、いずれも「適切なタイミングで高く売る」ことが肝心です。
借り換え戦略|金利圧縮&修繕費用の資金調達に
借り換え(リファイナンス)戦略は、現在利用中のローンをより有利な条件のローンに組み替えることで、投資収支を改善したり追加資金を得たりする出口戦略です。
金利負担を圧縮してキャッシュフローを向上させると同時に、必要に応じて修繕費用や新規投資の原資を捻出できます。
物件を売却しなくても資金繰りを整えることができるため、「持ち続けながら手元資金を確保する」柔軟な手法と言えます。
金利情勢や物件価値の変化に応じてローン条件を見直すことで、投資の効率を上げられる場合があります。
例えば、数年前に借りたローン金利が高めであれば、現在の低金利ローンに借り換えることで毎月の利息支払いを減らし、手残りを増やせます。
また、物件の担保評価額が購入時より上がっていたり、ローン残高が減っていたりする場合は、担保余力を活用して新たな融資を受けることも可能です。
これにより、大規模修繕の費用や追加の投資資金を調達することができます。
借り換え戦略のもう一つの利点は、融資条件の改善です。期間を延ばして毎月の返済額を抑えたり、元利均等返済から元金均等返済に変えて元金の減り方を加速させたりと、自分の戦略に合ったローンに組み替えることができます。
いずれにせよ、借り換えを成功させるには金融機関との交渉が鍵です。
借り換え戦略の具体例
地方で一棟アパート経営をする方をケースに具体例を紹介します。
当初、金利3.0%・期間25年のローンを組んでいました。運営開始から5年が経過し、幸い空室も少なく安定経営が続いたため物件の収益性が評価され、現在の担保評価額は購入時より上昇しています。
ちょうどローン金利の固定期間(5年)が切り替わるタイミングでもあったため、地元銀行に借り換えを打診しました。
結果、金利1.5%・期間20年という好条件で新規融資を受けられることになり、毎月の返済額は数万円規模で減少しました。
同時に、評価額が上がった分の余裕を使い追加で500万円の融資も取り付け、大規模修繕のための資金を確保しました。
これにより物件を売らずに済むどころか、リフォームで物件価値を高め家賃アップも見込める状況を作り出したのです。
このように借り換え戦略は、上手く活用すれば「持ちながら儲ける」道を開く、有力な出口オプションとなります。
借り換え戦略は、不動産を保有しつづけながら収益構造を改善できる点が最大の魅力です。市場金利の変動や物件価値の向上を見逃さず、タイミングが来たら積極的に借り換えを検討しましょう。
大規模修繕|保有継続のための“先延ばし型”出口
大規模修繕を実施する戦略は、「物件を売らずに保有継続するための先延ばし型の出口戦略」と位置付けられます。
建物の老朽化に伴い避けられない大型出費に備え、計画的に修繕を行うことで物件の寿命を延ばし、引き続き賃貸経営を続ける戦略です。
いわば「売却せずにもう一勝負する」選択肢であり、適切に実行できれば家賃収入の源泉を守り抜くことができます。
不動産は経年劣化とともに修繕コストが増大し、放置すれば居住環境の悪化による空室増や資産価値の下落を招きます。
そこで定期的に大規模修繕工事を行うことで、建物の機能や美観を回復・向上させ、入居付けの悪化や賃料下落を防ぐことが可能です。
修繕に適したタイミングを見極め、必要な資金を用意できるかがこの戦略のポイントになります。
大規模修繕の具体例
築20年のRC造マンションの所有者の大規模修繕の具体例を紹介します。
築20年も経つと、外壁のひび割れや設備の老朽化が目立ってきたため、築25年目に大規模修繕を実施する計画を立てました。
事前に工事内容と見積もりを取り、費用は約3000万円と判明。所有者は10年前から毎月家賃収入の一部を積み立てており、自己資金2000万円を確保していました。
不足分1000万円は銀行から修繕目的の融資を受けることに成功し、屋根・外壁・配管等の全面改修工事を実行しました。
その結果、建物は新築時に近いレベルまでコンディションが回復し、入居者からの評判も向上して空室期間が短縮するという好影響が現れました。
さらに、修繕済み物件という安心感から購入希望者の評価も高まり、仮に将来売却する場合も有利に働く見込みです。
大規模修繕戦略は、出口を先送りにしつつ物件価値を維持・向上させる「攻めの守り」の戦略です。
重要なのは事前の備えと判断基準です。将来の大きな出費に備えて資金計画を立て、修繕すべきか売却すべきかの見極めポイント(修繕費用と見込まれる収益のバランス)を明確にしておきましょう。
購入時に出口戦略を考えないとどうなる?|3つの失敗例

購入時に出口戦略を考えなかった場合の失敗例を紹介します。
高値掴みで売却できない詰み状態に
一つ目の失敗例は、相場より高い価格で物件を掴んでしまったために、売却してもローン残債が返済できない、完全に“詰み”の状態に陥るケースです。
高値掴みは不動産投資において致命的なミスであり、絶対に避けたい出口戦略の失敗パターンです。
物件を高値で買ってしまうと、将来売却しようとしても購入時の価格以上で売れない可能性が高くなります。
仮に市場価格が購入時と同水準または下落していた場合、売却額ではローンを完済できず、手元資金を持ち出さなければならなくなります。
残債割れ(オーバーローン)の状態では、実質的に売却の選択肢がなくなってしまうのです。
修繕資金が用意できず老朽化で物件価値が下がる
二つ目の失敗例は、将来の大規模修繕や設備更新に必要な修繕資金の備えを怠ったため、物件の老朽化に対応できず苦境に陥るケースです。
修繕費用を用意できないと建物の状態は悪化する一方で、それに伴い入居者離れや家賃低下も招き、収支がさらに悪化します。
建物はいずれ必ず古くなり、屋根・外壁工事や給排水設備の交換などまとまった支出が必要になります。
出口戦略を考えずに物件を買った人は、この長期的なコスト計画が不足していることが多いです。
毎月のキャッシュフローばかりに目が行き、10年後20年後に数百万円〜数千万円単位の修繕費が発生し得る現実を見落としてしまうのです。
その結果、築年数が進んで外観や設備が古びても何も手を打てず、家賃収入が減る一方で、故障対応など細かな修繕費はかさむため、収支状況はさらに悪循環に陥ってしまうのです。
融資が通らない=逃げ道ゼロになる
三つ目の失敗例は、追加融資や借り換えといった金融面の出口が閉ざされてしまうケースです。
物件を売却することも難しく、融資によるテコ入れもできない状況に陥り、事実上「逃げ道ゼロ」となるリスクです。
特に昨今は金融機関の融資姿勢が変化しやすく、計画通りに資金調達できない可能性を常に念頭に置いておかなければなりません。
出口戦略を考えずに強引な資金計画で購入すると、後から融資が行き詰まってどうにもできなくなる危険があります。
他にも不動産投資の失敗事例はたくさんありますが、多くの失敗事例を知ることでご自身の投資に生かすことができます。
以下の記事では、不動産投資の失敗率や失敗事例を紹介しているので、こちらも参考にしてください。

プロが実践する出口戦略を見据えた不動産投資の3つのポイント

成功している不動産投資家は、購入時点で出口戦略を意識しています。
物件選びや資金計画の段階から「将来どう手放すか」を見据えているのです。不動産投資では、購入と売却はセットであり、優れた投資家ほど出口までを計算して買っています。
ここでは、出口戦略を意識した買い方のポイントを3つ紹介します。
とにかく安く買うことを意識する
不動産投資に成功しているオーナーがとにかく口を揃えて言うことが「とにかく安く買うこと」です。
物件を安く買えば、売却益を出しやすく、借入額を抑えられるため資金繰りにも余裕が生まれます。
担保評価にもゆとりができ、追加融資にも有利です。一方で高値掴みは、出口戦略を狭める原因となるため避けるべきです。
購入価格が低ければ、多少安く売っても損を回避しやすくなります。ローン返済も軽くなり、キャッシュフローも良好。
その余剰資金で修繕や繰上返済ができ、さらに出口が安定します。含み益のある状態であれば、金融機関の評価も高まり、借り換えや追加融資にも強くなります。
安く買うことでリスクへの備えにもなり、柔軟な対応が可能になるのです。
出口戦略の自由度は「どれだけ安く買えたか」に比例します。売却益や融資余力、キャッシュフローの原点は購入価格にあります。相場より高く買うくらいなら、見送る勇気も必要ですよ。
収支バランスと返済スピードに注目せよ
収支バランスと返済スピードに注目することも大切です。
毎月の収支がプラスで、元金返済が着実に進む物件を選ぶことで、将来的に残債と物件価値の差が広がり、売却時に多くの現金を得られます。
家賃から経費・ローンを引いた手残りが大きいほど、投資は安定します。
成功投資家は必ず手残りが出る物件しか買いません。手残りがあれば、空室や修繕への対応ができ、繰上返済や資金貯蓄にも充てられます。
さらに返済期間が短いほど、元金の減りが早く資産の純資産化が進み、デッドクロス対策にもなり、出口戦略が安定します。
購入時に「何年後に残債はいくらで、手元にいくら残るか」を計算することが、出口戦略の成否を左右します。
収支と返済の計画が立たない物件は、見送る判断も重要です。不動産投資を成功させるためには、数字で未来を描ける物件を選びましょう。
「融資が通るか」より「出口が取れるか」で判断する
成功している投資家は「銀行が融資してくれるか」よりも「将来きちんと売却できるか」を重視します。
融資が通るからといって、それが良い物件とは限りません。
銀行の基準と市場価値は別です。将来の買い手が融資を受けやすいか、流動性の高い物件かを見極めることが重要です。
再建築不可や狭小物件は売却しにくく、出口が取りづらくなります。
大事なのは、金融機関ではなく「自分の出口戦略」で投資判断をすること。出口を起点に物件を選ぶことが、長期的に勝ち続ける投資家の思考です。
物件タイプ別・出口戦略の注意点
物件の種類によって、出口戦略の取りやすさや注意点は大きく異なります。出口戦略を成功させるには、物件タイプごとの特徴を理解した上で、売却や借り換え、修繕などの選択肢を柔軟に組み合わせていく必要があります。
ここでは、「戸建て」「一棟マンション」「ワンルームマンション」の3種類に分け、それぞれの出口戦略における注意点と成功のポイントを解説します。
戸建て|エリアと築年数が出口の明暗を分ける
戸建て投資における出口戦略では、「立地」と「築年数」が最重要ポイントとなります。特にファミリー層向けに賃貸されるケースが多いため、周辺の学校区や治安、生活利便性などが再販価値に直結します。
築古の戸建ては安く仕入れやすい反面、出口では「更地」「古家付き土地」「リフォーム済み戸建て」として売却方法が分かれるため、戦略設計が複雑です。また、戸建ては収益物件として売るというよりも、実需向け(自宅用途)で売却されることが多いため、買主の層が変わる点にも注意が必要です。
例えば、築40年の戸建てを格安で購入し、DIYやリフォームで住環境を整えた上で、子育て層向けに販売したケースでは、土地評価×再建築性の高さが売却の決め手となりました。
一方で、再建築不可物件や過疎地の戸建てでは需要が極端に少なく、出口が塞がってしまうこともあります。あらかじめ「実需向けに売れる立地か」「土地活用できるエリアか」を見極めたうえで、購入段階から出口設計を行うことが成功への近道です。
一棟アパート・マンション|売却か保有継続か分岐点を見極める
一棟アパート・マンションは投資規模が大きいため、出口戦略の成否が資産形成全体に与える影響も大きくなります。出口戦略の軸は「利回り評価による売却」か「資産保有としての継続運用」の2択に分かれます。
また、購入当初に比べ金利環境が変化していれば、借り換えやリファイナンスを検討することも必要です。修繕や共用部の美観維持、エレベーター・消防設備の更新など、大規模支出が避けられない一棟物件では、5年後・10年後のキャッシュフロー予測を立て、保有と売却の分岐点を設計しておくことが求められます。
成功しているオーナーは「利回り7%を切ったら売却」「大規模修繕前に出口を取る」といったルールを設け、感情ではなく数値で判断を下しています。規模が大きいからこそ、戦略なき保有はリスクを高めると理解しておくべきです。
区分ワンルームマンション|流動性は高いが出口は慎重に
区分ワンルームマンション投資は、比較的少額から始められる手軽さと、物件の流動性の高さが魅力です。しかし、出口戦略として「高値で売却する」難易度は意外と高く、慎重な判断が求められます。
特に注意すべきは、「収益還元法」による価格評価が主となる点です。仮に家賃が下落していたりすると、表面利回りが低下し、売却価格が落ち込む傾向があります。
また、競合物件が多いため、立地・築年数・管理体制などで優位性を確保していないと、売却時に埋もれてしまうリスクもあります。出口を意識するなら「都心3区」「駅徒歩5分以内」「築浅または大規模修繕済み」といった条件を揃えることが望ましいです。
具体例として、築15年の区分ワンルームを購入後、3年間運営し、家賃下落が進行したため売却を検討したケースがあります。運よく駅近・角部屋で設備の状態が良好だったため、利回り重視の投資家に対してスムーズに売却できましたが、それは「出口を意識して買っていた」からこそ可能だったと言えるでしょう。
手軽に始められる区分ワンルーム投資だからこそ、購入時から「いつ・誰に・いくらで売るか」を具体的にイメージしておくことが成功の鍵になります。
まとめ
不動産投資における「出口戦略」とは、物件を最終的にどう扱うかを事前に計画することであり、売却に限らず「借り換え」や「大規模修繕による継続保有」など複数の選択肢があります。
出口戦略を考えずに投資を始めると、収益性の低い物件を手放せず損失を抱え続けるリスクも。
逆に、購入前から出口を想定していれば、リスクを抑えつつ最適なタイミングで利益確定や資金再投下が可能になります。
不動産投資で成功するには、「どの方法で・いつ・いくらで」物件を手放すかという出口のシナリオを描くことが重要であり、投資判断の出発点とも言えるのです。
”元ゴールドマン・サックス不動産投資家が教える失敗しない不動産投資の成功法則”を
LINE友だち限定でお伝えします。
LINE登録でもらえる豪華6大特典
①数字とエビデンスに基づく投資判断マニュアル
②自分に最適な「融資」を見つけるガイド
③不動産購入前に必ず確認すべき「リスク」と「資料」
④ 「お宝物件」発掘のための効果的な探し方
⑤『不動産購入「現地調査」で確認すべきチェックリスト
⑥不動産運営にかかる収益費用の把握の仕方
LINE友だち追加してくれた方だけに、登録者6万人のYouTubeでも話せない情報をお届けしています
小原正徳の公式LINEはこちらから
▼スマホはこちらから限定情報をGET!▼
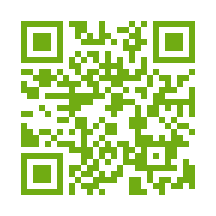

【監修者情報】不動産投資家 小原 正徳
1981年4月6日生まれ 不動産投資家
東京大学卒業後、EYグループ不動産部門、
ゴールドマン・サックスグループ不動産ファンド部門を経て
2016年に東京都新宿区株式会社不動産科学研究所で独立
2022年には総資産20億円を形成
同年、新たなチャレンジとして不動産投資スクールを開校し、自身の培ったノウハウの提供を開始
株式会社不動産科学研究所 代表取締役
宅地建物取引士
不動産鑑定士
不動産証券化協会認定マスター