この記事で紹介している内容
- 利回りの計算方法(表面・実質・想定利回りの3つ)
- 高い利回りが必ずしもいいとは限らない理由
- 今後は利回りだけでなく「総合収益率」を見る時代に
不動産投資の利回りについて「どのくらいの数値だといい?」「どうやって計算すればいい?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
利回りは「高ければ高いほど良い」というイメージを持っている方も多いと思います。
しかし、実際に高利回りが必ずしも良い物件とは言えず、逆に利回り2%でも立地や需要、築年数等で見ると良い物件と言えるものも少なくありません。
そこで本記事では、利回りの本質を見抜いてもらうために、利回りの種類や計算方法、高利回りが必ずしも良い物件とはいけない理由を紹介します。
利回りに関する最新トレンドにも言及しているので、これから不動産投資を考えている方や、過去に利回りで失敗した経験がある方は参考にしてください。

【監修者情報】不動産投資家 小原 正徳
1981年4月6日生まれ 不動産投資家
東京大学卒業後、EYグループ不動産部門、
ゴールドマン・サックスグループ不動産ファンド部門を経て
2016年に東京都新宿区株式会社不動産科学研究所で独立
2022年には総資産20億円を形成
同年、新たなチャレンジとして不動産投資スクールを開校し、自身の培ったノウハウの提供を開始
株式会社不動産科学研究所 代表取締役
宅地建物取引士
不動産鑑定士
不動産証券化協会認定マスター
”元ゴールドマン・サックス不動産投資家が教える失敗しない不動産投資の成功法則”を
LINE友だち限定でお伝えします。
LINE登録でもらえる豪華6大特典
①数字とエビデンスに基づく投資判断マニュアル
②自分に最適な「融資」を見つけるガイド
③不動産購入前に必ず確認すべき「リスク」と「資料」
④ 「お宝物件」発掘のための効果的な探し方
⑤『不動産購入「現地調査」で確認すべきチェックリスト
⑥不動産運営にかかる収益費用の把握の仕方
LINE友だち追加してくれた方だけに、登録者6万人のYouTubeでも話せない情報をお届けしています
小原正徳の公式LINEはこちらから
▼スマホはこちらから限定情報をGET!▼
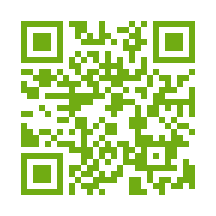
不動産投資における利回りとは?

不動産投資における利回りとは、投資した金額に対して年間でどれだけの収益(リターン)が得られるかを示す指標です。
利回りを見ることで「この不動産に投資すべきか」「投資資金を何年で回収できるか」の判断材料になります。
たとえば、物件価格2,000万円で年間家賃収入が100万円なら、利回りは5%です。
この数値が高ければ高いほど、収益性が高いと考えられます。
しかしながら、利回りは物件ごとの収益性だけでなくリスクもあらわしており、利回りが高い物件ほど価格が安く、何らかのリスク要因を抱えているケースが多いです。
このため、単に数字の高さだけで飛びつくのは禁物です。
「表面」「実質」「想定」の違い
利回りにはいくつか種類があります。
基本となるのは表面利回りと実質利回りで、さらに将来予測を織り込んだ想定利回りという考え方もあります。
表面利回りと計算方法
表面利回り(グロス利回り)とは、満室想定の年間家賃収入 ÷ 物件価格で計算されるシンプルな利回りです。
経費や空室損失を一切考慮しない「表示上の利回り」で、不動産広告などでもっとも手早く比較するために用いられます。
表面利回り(%)= 年間満室家賃収入 ÷ 物件購入価格 × 100
例えば、家賃10万円/月の物件(満室想定年間収入120万円)を2,400万円で購入した場合、表面利回りは5.0%となります(120万円÷2,400万円)。
表面利回りは経費や空室損失を計算に入れないため、すぐに収益性を比較できる反面、詳細な利回りを計算できない点に注意が必要です。表面利回りは物件を初期スクリーニングする目安として捉え、本格的な検討時には必ず次の実質利回りを算出しましょう。
実質利回りと計算方法
実質利回り(ネット利回り)とは、物件の実際の純収益 ÷ 物件価格で計算される利回りです。
ここで言う純収益とは、満室想定家賃から空室損失や運営費(管理費・修繕費・保険料など)を差し引いたものです。
実質利回り(%)= 純収益(年間家賃収入 − 空室損 + 経費差引後) ÷ 物件価格 × 100
実質利回りは表面利回りより一歩踏み込んだ指標で、より現実的な収益性を示します。
経費や空室リスクを織り込むため、一般に表面利回りより2〜3割程度低い数値になる傾向があります。
実質利回りは主に個人投資家が長期保有の収益性を判断する際に重視する指標です。
また、不動産会社によって経費に何を含めるか定義が異なるため、必ず確認しましょう。
実質利回りを計算することで、表面利回りだけでは見えなかった維持管理コストや空室リスクが数字に表れます。
「思ったより利回りが出ない」物件を見極めるために、購入前に必ず実質利回りを算出しましょう。
想定利回りと計算方法
想定利回りとは、将来的な家賃変動や空室率、修繕費用の増減などの前提条件の上で計算した利回りです。
表面利回りや実質利回りに「数年後の空室率10%、家賃下落20%、修繕費8万円/年」等のシナリオを設定し、将来の収益見込みで計算し直したものになります。
つまり、「将来○○という前提ならこのくらいの利回りになるだろう」という「見込み利回り」ということです。
このため、想定利回りには明確な計算式があるわけではないものの、想定家賃収益に修繕費や空室を想定した家賃収入の合計を差し引いた金額を入れることで計算できます。
想定利回り(%)=年間想定家賃収入÷物件購入価格×100
h3: 高利回り物件が必ずしも良いとは限らない
利回りの高さ=儲けの大きさと考えるのは危険です。
利回りは「どれほどのリスクを取って得られる収益か」を示す指標でもあります。
投資の原則はハイリスク・ハイリターンであり、安全な資産ほど利回りは低く、不確実な資産ほど高くなる傾向があります。
不動産投資も同様で、高利回り物件を探す行為は、高リスク物件を探しているのと同義です。
たとえば、一等地の築浅マンションが利回り4%でも人気なのは安全性と資産価値が高いからです。
一方、地方の築古アパートで利回り20%超なら、需要低迷や老朽化などのリスクが潜んでいる可能性があります。
極端な高利回りは入居者がいなければ意味がなく、逆に低利回りでも将来の値上がりを狙う投資もあります。
つまり、利回りは単なる収益率ではなく、「リスクと将来性を測る物差し」として理解すべきなのです。
不動産投資の利回りの最低ライン・相場
不動産投資の利回りの最低ラインや相場についてですが、物件の立地や条件によって良しとされる利回りが異なるので、何%以上だから安心、といった基準はありません。
しかしながら、一般的には表面利回りで5%以上、実質利回りで3%以上が一つの目安とされています。
これは、家賃収入から経費を差し引いても赤字にならず、長期的に投資資金を回収できる最低ラインを意味します。
もちろん、地域や物件の種類によって相場は変動します。
| エリア・物件タイプ | 表面利回りの相場 | 特徴 |
|---|---|---|
| 都心の区分マンション | 3〜5% | 空室リスクが低く安定型 |
| 郊外の一棟アパート | 6〜9% | 家賃下落・修繕リスク高め |
| 地方・築古物件 | 10%以上 | 表面上高利回りだが流動性低い |
初心者がまず狙うべきは、「実質利回り3〜4%でも安定的に入居が続く堅実な物件」です。
数字の高さではなく、どれだけ安定したキャッシュフローを維持できるかを重視することが、失敗しない第一歩です。
目的によって見るべき利回りは違う

毎月のキャッシュフローを重視するのか、将来的な売却益を狙うのかによって、利回りの見るべきポイントや判断基準は大きく変わります。
また、同じ物件でも融資条件によって実際の手残りは変動します。
このため、不動産投資の目的と資金計画をセットで考えることが重要です。
ここでは代表的な投資スタイルごとに、どの利回りをどう活用すればよいか解説します。
キャッシュフロー重視型の利回りの見方
毎月のキャッシュフローを重視する場合、表面利回りではなくローン返済後の「実質利回り」で判断することが重要です。
キャッシュフロー率=(家賃収入−空室損−運営費−年間返済額)÷物件価格×100
上記のように算出し、実際に手元に残る割合を確認します。
フルローンでは手残り利回りが1〜2%程度にとどまることも多く、金利上昇や空室発生で赤字転落するリスクもあります。
そのため、投資判断時には「金利+1%」「家賃−10%」など複数シナリオでシミュレーションし、最悪でもキャッシュフローがマイナスにならないかを確認することが重要です。
売却益(キャピタルゲイン)重視型の利回りの見方
キャピタルゲインを狙う投資では、購入時の利回りと市場利回りの差=価格差に注目します。
たとえば、周辺が利回り8%のエリアで自分だけ10%で買えれば、将来8%相場で売却した際に価格上昇分が利益となります。
これは「利回りと価格が反比例する」関係を利用した考え方です。
ただし、転売には税金や売却コスト、相場変動などのリスクが伴うため、数年の保有を前提に出口戦略を明確にすることが重要です。
融資条件(金利・期間・自己資金)と利回りの関係
不動産投資では、金利・融資期間・自己資金割合によって利回りが大きく変わります。
借入条件次第で、同じ物件でもキャッシュフローがプラスにもマイナスにもなり得ます。
自己資金を多く入れれば返済負担が減り安全性は高まりますが、自己資金利回り(CCR)は低下するのです。
一方、自己資金を減らせばリスクは増すものの、CCRは上昇します。つまり安全性と効率はトレードオフの関係にあります。
近年融資のフルローンが出にくくなっている
最近はフルローンがほとんど出なくなり、8~9割融資が一般的になっています。つまり、頭金や諸費用を含めた“自己資金”をどれだけ投入するかが投資成績を左右する時代です。
そこで僕は最終判断の基準をCCR(Cash on Cash Return=自己資金利回り)に置いています。
CCRとは、投入した現金に対して毎年どれだけの現金が戻ってくるかを示す指標で、計算式は『キャッシュフロー ÷ 自己資金 ×100』。
この数字を見れば「自己資金を何年で回収できるか」が直感的に分かります。僕の場合、理想は20%、最低でも15%を目安にしています。都心では10%前後でも合格ですが、リスクの高い地方物件なら25%以上を狙います。」
CCR(Cash on Cash Return)は、年間手残りキャッシュフローを自己資金で割った「自己資金利回り」です。
CCR10%以上(約10年で資金回収)が一つの目安で、15%以上なら優良投資とされます。
ただし、極端に高いCCRは高リスク物件の可能性もあります。
融資を活用する際は、返済比率とCCRのバランスを重視し、自己資金を入れすぎず、かつキャッシュフローが安定する融資条件を設計することが重要です。
不動産投資の利回りを考える時の重要な5つのポイント

不動産投資の利回りで失敗しないためにも、利回りを考える時の重要な5つのポイントについて紹介します。
実質利回りを必ず計算する
物件広告などでは高い表面利回りが強調されがちですが、購入判断では必ず実質利回りを計算しましょう。
表面利回りには経費も空室リスクも織り込まれていないため、そのまま鵜呑みにすると「話が違う」という結果になりかねません。
実質利回りを出すには、まず現状の家賃や共益費収入の合計から想定空室ロスを引き、さらに管理費・修繕費・税金・保険料など年間経費を差し引きます。
そこまでして初めて、物件の本当の収益力(純利益)が見えてくるのです。
例えば、表面利回り12%(満室想定)の築古アパートでも、空室率10%、運営費20%とかかれば実質利回りは約8.6%に下がります。
同じ12%でも空室だらけなら0%、満室続きなら12%と振れ幅が大きいといえます。
「経費を引いても利回りが高いか」が肝心であり、表面的な数字に惑わされないことが重要です。
補修や修理といった修繕費も計算しておく
利回り計算にあたっては、税金などの表面的な経費だけでなく、将来発生する大規模修繕費や原状回復費も見込んでおきましょう。
築年数が古い物件ほど維持や管理にお金がかかり、その分実質利回りは目減りします。
このため、今後数年で必要となる工事の費用を試算してください。
例えば「築20年で屋上防水に200万円、給湯器交換に50万円かかりそう」といった具合です。
こうした将来コストを毎年平準化して見積もれば、実質利回りからさらに数%減と判断できます。
特に初めての物件では見落としがちなので、最初から家賃収入の○%は修繕積立くらいの気持ちで計画しておきましょう。
そうすれば突発的な出費にも耐えやすく、利回り計画のブレも小さくなります。
家賃が下落する可能性も考慮する
現在の家賃収入が将来も続くとは限りません。
賃料は景気や競合、新築供給などで変動し、築古や地方物件では家賃を下げなければ入居が決まらないこともあります。
利回りを「家賃×満室」で計算すると、実際には-1万円の値下げが必要になるケースもあるため注意が必要です。
シミュレーションでは家賃下落(例:5年後に10%減)や空室率(都心5%、地方15%など)を織り込みましょう。
不動産会社の収支表を見る際も、前提の空室率が現実的か確認することが大切です。
また、長期保有では家賃改定にも注意が必要です。
普通借家契約では下げやすく上げにくいため、物価上昇があってもすぐ反映できないことがあります。
収益計画は保守的に立て、想定より家賃が下がっても耐えられるか確認しておくことが重要です。
極端に高い・低い利回りの物件に注意する
市場相場とかけ離れた極端な利回りの物件は要注意です。
表面利回りが極端に高い物件は、その理由を突き止めることが大前提です。
「利回り20%超!」「家賃年収◯百万円でこの価格!」など派手な謳い文句の裏には、「築年数が相当古い」「駅から遠い」「借地権付き」など、何かしら価格を押し下げている要因が潜んでいます。
そうした物件は前述の通り空室・修繕・流動性といったリスクが高く、実質利回りとのギャップも大きい傾向があります。
購入検討の際は、なぜ売主はその価格で売ろうとしているのかを冷静に考え、不明点は必ず専門の仲介会社に確認しましょう。
逆に極端に利回りが低い物件も、初心者にとっては危険な場合があります。
利回りが低い物件は一般に立地が良く空室リスクが低い(都心・築浅など)メリットがありますが、その分投資金額に対する利益が小さいため、少しの誤算で赤字に転落しかねません。
例えば都心の新築マンションで利回り4%だと、満室経営でも諸経費差引後はほぼトントン、1室空いただけで赤字というケースもあります。
自己資金に余裕があって「資産の保有」が目的なら低利回り物件も選択肢になりますが、収益を上げる目的なら低すぎる利回りは避けるのが無難です。
「高すぎる利回り」と「低すぎる利回り」はそれぞれ理由があるので、極端な数字には惑わされないよう、なぜその利回りなのかを突き止めるようにしてください。
物件の出口戦略(売却など)も想定しておく
「安く買って長期保有すれば安心」と考えるのは危険です。
賃貸経営には寿命があり、建物老朽化や修繕費の増大で採算が合わなくなる時期が来ます。
このため、購入した物件において「将来どう回収するか」という出口戦略を最初から設計しておくことが重要です。
高利回り物件(築古戸建てなど)ほど売却時の流動性が低く、買い手が付きにくい傾向があります。
購入前に「10年後に土地値で売却」「更地化」「相続継続」など複数の出口を想定し、逆算して購入価格を判断しましょう。
また、ローン残債が売却額を上回ると売れなくなるため、融資期間と残債推移=出口戦略と考える必要があります。
特に短期転売を狙う場合は、楽待や健美家などのポータルサイトで市場動向を確認したり、仲介会社に「この物件を◯年後に売るとしたらいくらで売れそうか」意見を聞くなど、具体的な出口戦略プランを確認しておきましょう。
出口戦略については以下の記事も参考にしてください。

利回りだけでなく「総合収益率」で判断する時代へ

筆者である小原は、日本の不動産投資市場も徐々に「総合収益率」で物件を判断する視点が求められる時代になりつつあると考えています。
というのも、海外では、「インカムゲイン+キャピタルゲイン」の総合的なリターンを追求する動きが広がっているからです。
海外投資家が重視する「インカム+キャピタル」視点
海外の不動産投資家にとって、物件の評価はトータルリターンが基本です。
不動産を取得してから売却するまでの全期間でどれだけリターンを生み出すか、すなわち年間のインカムゲイン(賃料収入)に将来のキャピタルゲイン(売却益・損)を加えた総合収益率を重視しています。
例えば、アメリカやヨーロッパでは、保有中の表面利回り(インカム)は2〜3%程度と低いケースがほとんどです。
しかし、毎年5%程度の資産価値上昇(キャピタルゲイン)が見込まれるため、トータルでは年間7〜8%の総合収益率になります。
つまり、彼らは単年の家賃収入だけでなく、「値上がり益を含めたリターン全体」で投資判断をしているのです。
一方、日本では依然としてインカム(家賃収入)中心の利回りが投資判断の基準になっています。
そのため「利回り何%なら良い物件か?」という議論が成立しますが、海外ではむしろ「年間トータルでどれだけ資産が増えるか」に焦点を当ています。
インフレ進行で変わる日本の不動産投資の考え方
長らくデフレ傾向だった日本も、近年はインフレ率の上昇と賃金アップが見られ、「物価が上がらない国」ではなくなりつつあります。
これに伴い、不動産市場でも賃料上昇の余地が生まれました。
以前は「家賃は下がる一方」という前提で堅実なインカムを得ることが重視されてきましたが、今後は家賃も物件価格も上がる可能性が高いです。
実際、2020年から2025年にかけて都心部のオフィスや住宅で家賃が上向き、物件価格も上昇トレンドが続いているので、海外ファンドも「日本の不動産はまだ割安だ」と捉えて投資を強めています。
インフレの環境では、資産価値の目減りを避けるため不動産への投資が増える傾向があり、それが価格上昇を後押しする面もあります。
また、インフレによって得られる実質的な債務圧縮により、レバレッジを利かせた投資も有利になります。
その結果、キャピタルゲイン狙いや物件を改良して価値を高めるバリューアップ戦略にも追い風が吹いています。
これらを踏まえると、今後は利回りを重視するだけでなく、売却益を増やすことも考えて「数年後に価値の上がる物件」を見つけることが重要になってくるのです。
日本ではまだまだ利回りだけを不動産投資の指標にしていますが、いち早く「インカム+キャピタル」の視点で物件を探すことで、堅実で将来展望のある物件に出会えるはずです。
このような最新の不動産投資トレンドや投資の考え方は公式LINEでも配信しています。
”元ゴールドマン・サックス不動産投資家が教える失敗しない不動産投資の成功法則”を
LINE友だち限定でお伝えします。
LINE登録でもらえる豪華6大特典
①数字とエビデンスに基づく投資判断マニュアル
②自分に最適な「融資」を見つけるガイド
③不動産購入前に必ず確認すべき「リスク」と「資料」
④ 「お宝物件」発掘のための効果的な探し方
⑤『不動産購入「現地調査」で確認すべきチェックリスト
⑥不動産運営にかかる収益費用の把握の仕方
LINE友だち追加してくれた方だけに、登録者6万人のYouTubeでも話せない情報をお届けしています
小原正徳の公式LINEはこちらから
▼スマホはこちらから限定情報をGET!▼
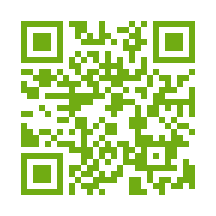
まとめ
不動産投資の利回りは、数字の高さではなく“その前提と意味”を読み解くことが何より重要です。
表面・実質・想定の3種類を正しく区別し、「どんな条件下でその数字が成り立つのか」を理解しましょう。
特に、不動産投資で使われるのは経費などを無視した「表面利回り」になるため、投資を検討する際には「実質利回り」で算出するようにしましょう。
正しく利回りを理解し、総合収益の視点で投資を組み立てれば、マイナスになりにくい長期的に安定した資産形成が可能です。
焦って物件を探すのではなく、データと戦略に基づいた「堅実な投資判断」を心がけましょう。
また、今回の内容は動画でも解説しています。
気になる方は以下の動画も参考にしてください。








