「不動産投資をするために動いているけど、融資が全然通らない」
「どうしてあの人は同じ年収なのに次々と物件を増やしているのか?」
その答えは、物件の目利きではなく融資の準備力にあります。
不動産投資は「良い物件を探すこと」が勝負だと思われがちですが、実際には違います。銀行が首を縦に振らなければ、どれほど優良な物件でも手に入りません。
そして、この「融資が通るかどうか」は、面談の日に決まるのではなく事前の準備段階で9割が決まっているのです。
本記事では、成功する投資家が実践している融資戦略を徹底解説します。
「自己資本の積み上げ方」「銀行の攻略ルート」「面談での伝え方」あなたがこれを知らずに物件探しをしているなら、時間もお金も無駄にしているかもしれません。
一つ一つ詳しく解説するので、不動産投資を検討している方や、融資が受けられずに悩んでいる方は参考にしてください。

【監修者情報】不動産投資家 小原 正徳
1981年4月6日生まれ 不動産投資家
東京大学卒業後、EYグループ不動産部門、
ゴールドマン・サックスグループ不動産ファンド部門を経て
2016年に東京都新宿区株式会社不動産科学研究所で独立
2022年には総資産20億円を形成
同年、新たなチャレンジとして不動産投資スクールを開校し、自身の培ったノウハウの提供を開始
株式会社不動産科学研究所 代表取締役
宅地建物取引士
不動産鑑定士
不動産証券化協会認定マスター
”元ゴールドマン・サックス不動産投資家が教える失敗しない不動産投資の成功法則”を
LINE友だち限定でお伝えします。
LINE登録でもらえる豪華6大特典
①数字とエビデンスに基づく投資判断マニュアル
②自分に最適な「融資」を見つけるガイド
③不動産購入前に必ず確認すべき「リスク」と「資料」
④ 「お宝物件」発掘のための効果的な探し方
⑤『不動産購入「現地調査」で確認すべきチェックリスト
⑥不動産運営にかかる収益費用の把握の仕方
LINE友だち追加してくれた方だけに、登録者6万人のYouTubeでも話せない情報をお届けしています
小原正徳の公式LINEはこちらから
▼スマホはこちらから限定情報をGET!▼
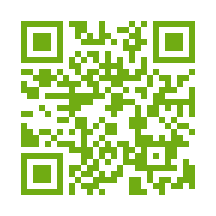
不動産投資は物件探しより融資戦略が9割

不動産投資で成功するためには、実は物件探しよりも「融資戦略」が重要です。
良い物件を見つけても融資が通らなければ購入できないため、まず融資ありきで物件条件を逆算する思考法が成功の鍵となります。
融資を軸に計画を立てることで、自分が現実的に手に入れられる物件の規模や価格帯を絞り込め、効率的な物件探しが可能になります。
例えば「年収〇〇万円だから借りられるのは△△万円程度まで」と融資の目安を把握すれば、最初からその範囲内の物件に集中できます。
失敗しやすい方法として、「物件→融資」の順で動くと、せっかく見つけた物件が融資NGで無駄になる可能性があるため、まずは融資についての知識を身に着けるべきです。
融資の全体像を理解する

具体的な戦略に入る前に、まず不動産投資における融資の基本的な枠組みを押さえておきましょう。
融資にはいくつか種類があり、銀行ごとに審査基準や条件が異なります。
代表的なのが「アパートローン」と「プロパーローン」の2つです。
アパートローンとプロパーローンの違い
アパートローンとは、主に個人向けに金融機関が用意した不動産投資専用のローン商品です。
一方、プロパーローンとは、銀行が独自の基準で審査し保証会社を介さずに実行するオーダーメイド型の融資のことです。
アパートローンとプロパーローンの違いをまとめました。
| 項目 | アパートローン | プロパーローン |
|---|---|---|
| 保証の有無 | 信用保証会社による保証が必要(保証料を支払う) | 保証会社不要(銀行がリスク負担) |
| 審査基準 | 所定の商品基準に沿った審査(比較的通りやすい) | 銀行独自の厳しい審査(実績や担保重視) |
| 融資金額上限 | 商品ごとに上限額が設定されることが多い | 個別案件ごとに決定(明確な一律上限なし |
| 金利相場 | 年2~5%前後(保証料込みでやや高め) | 案件により1~3%台も可能(条件次第で低金利も) |
| 融資期間 | 建物の耐用年数内が目安(最長30年前後) | 案件ごとに設定。場合によっては耐用年数超も可 |
| 自己資金 | 条件次第で自己資金0~10%でも可 | まとまった自己資金が必要(20%以上が目安) |
アパートローンは属性基準(年収・勤続・職種など)が中心で、審査回答は3日〜1週間程度と速い一方、総与信は年収倍率(目安:〜10倍)や商品上限で頭打ちになりやすく、総額1〜2億円前後で止まるケースが多いのが実態です。
一方でプロパーローンは案件ごとにオーダーメイドで、物件収支・賃貸需給・借り手のBS/PLまで精査されます。外部鑑定評価を取得する場合もあり、審査期間は1〜2か月以上を見込みます。
一般的に、初心者には各銀行の商品内容が明確なアパートローンが利用しやすく、プロパーローンは上級者向けと言われます。
自己資本比率10%と純資産×約10倍の目安
金融機関が不動産投資家に融資する際によく目安とする基準に「自己資本比率10%」と「純資産の約10倍まで」というものがあります。
本稿で言う「自己資本比率10%」は、(個人+法人合算の)貸借対照表における純資産÷総資産を指します。プロパーローンでは、ここが10%を切ると審査が極めて通りにくくなります。
なお、頭金○%は各案件のLTV(与信構造)の話で、自己資本比率とは別概念です。両者を混同しないようにしましょう。
目安として、純資産×約10倍まではプロパーでレバレッジが効きやすい一方、自己資本比率10%未満だと枠が広がりません。
次に純資産×約10倍の指標ですが、これは自身の純資産(自己資本)に対しておおむね10倍までの借入なら適正範囲という話です。
例えば純資産が3,000万円ある人なら、総借入残高は3億円程度までが上限目安という具合です。
不動産投資の融資成功する人だけがやっている5つのこと

融資の基礎を踏まえたところで、実際に融資戦略を駆使して物件を増やしている投資家たちの共通点を見ていきます。
単に知識があるだけでなく、実践で融資を引き出している人たちは、次の5つのポイントを押さえています。
- 自己資本を積み上げてから動く
- 金融機関マップを描いて戦略的に当たる
- 面談準備を徹底して“通る”説明をする
- 融資に好まれる物件条件を押さえる
- 長期保有を前提に出口戦略を描く
初心者のサラリーマン投資家や小規模な法人オーナーでも、このポイントを意識することで融資承認率を高め、堅実に資産を拡大することができるでしょう。
① 自己資本を積み上げてから動く
融資を有利に引くための基本は、「まず自己資本(自己資金)をしっかり蓄えること」です。
自己資金が潤沢であればあるほど、銀行からの信頼度は上がり、より好条件で融資を受けやすくなります。
成功している投資家は、物件購入に飛びつく前に自らの手元資金を増やすことに注力しています。
自己資本のスケールアップの基本式を確認しておきましょう。
- 自己資本(純資産)を増やす(本業/副業でのキャッシュ創出、あるいは売却益の計上)
- 増えた自己資本に応じてプロパー枠(概ね×10倍)が拡大
- 取得→運営→売却で自己資本がさらに厚くなる→次の枠が広がる
この拡大型ループに入ると、規模拡大が加速します。
※アパートローンのみだと総額1〜2億円付近で頭打ちになりやすいため、いつプロパーに橋渡しするかを逆算して動くのがコツです
本業・副業でのキャッシュ創出
本業の収入アップや副業による収入源の確保は、自己資本を積み増す王道パターンです。
サラリーマンであれば昇進や転職で年収を上げる努力、副業で毎月数万円でも収入を作るなど、地道なキャッシュ創出に励みます。
銀行は個人の返済能力を見る際に年収を重視するため、年収が上がれば融資上限額も引き上がる傾向があります。
また、副業収入があると返済原資に余力があるとみなされ、融資審査で有利に働くことがあります。
ただし、副業の種類によっては収入とみなされにくいケース(不安定な歩合制など)もあるため、着実に稼げる副業を選ぶことが大切です。
売却益での純資産増強
成功者の中には、購入した物件の売却益(キャピタルゲイン)を活用して自己資本を急増させている人もいます。
筆者の小原は、まずキャッシュを増やすことから始めました。キャッシュを増やしてからは、買って売るのサイクルを最適化し、築き上げた1億円という資産を10億円まで伸ばすことができました。
一棟マンションやアパートを数年運用して価値が上がったタイミングで売却し、その利益を自己資金に組み入れる戦略です。
例えば物件Aを購入後にリフォームや賃料アップで価値を高め、数年後に高値で売却して数百万円〜数千万円の利益を得れば、次の物件購入時に自己資金として投入できます。
こうした売却益は純資産を一気に厚くするため、銀行から見ると自己資本比率が改善し財務体質が強化された状態になります。
その結果、より大きな融資枠を得られるようになります。ただし、売却には税金(譲渡所得税)もかかるため、手残り資金を計算しつつ計画的に行う必要があります。
② 金融機関マップを描いて戦略的に当たる
一口に融資といっても、金融機関ごとに得意分野や融資姿勢は異なります。
成功者は、自分の状況に合った銀行・金融機関のリスト=「金融機関マップ」を作り、順序立ててアプローチしています。
漠然とあちこち当たるのではなく、「まず〇〇銀行と△△信金でトライし、次に条件次第で□□銀行へ…」といった具合に戦略を練っているのです。
政府系(公庫・保証協会付き)の活用
政府系金融とは、日本政策金融公庫(政府系の公的融資機関)や各地方自治体の制度融資(信用保証協会付き融資)などを指します。
これらは民間銀行に比べて創業者や小口の借入に相性が良く、不動産投資でも最初の一歩として利用されることがあります。
たとえば、日本政策金融公庫は比較的低金利で小規模物件購入資金を融資してくれるケースがあり、自己資金が少ない初心者が使いやすいです。ただし、公庫融資は基本的に個人事業主としての事業計画審査となるため、事前にしっかりと事業計画書を作成する必要があります。
また、自治体の制度融資(信用保証協会付き融資)は、地元の信用金庫や地方銀行を窓口として利用できます。
保証協会付き融資は保証協会が万一の返済を肩代わりする仕組みのため銀行も安心して貸しやすく、創業間もない法人や副業大家でも利用しやすいです。
ただし保証料が発生し、保証協会ごとに一人当たりの保証枠(通常数億円まで)に上限がある点は留意しましょう。
地方の信用金庫や信用組合の活用
多くの成功者は最初の物件購入時、地元の信金・信組から融資を引いてスタートしています。
信金・信組は営業エリア内の案件を好み、取引実績や紹介があると親身に相談に乗ってくれます。
最初に小さい物件でも良いので信金で実績を作り、きちんと返済実績を積めば、2棟目3棟目と融資枠を拡大してもらいやすくなります。まさに「地元密着の金融機関を味方につける」のが王道と言えます。
一方で、信金・信組の融資は金利がやや高め(おおむね年3%前後)になるケースが多い点には注意が必要です。
将来的には実績を積んで地方銀行やメガバンク、プロパーローンにもチャレンジするにしても、まずは信金で信用を築くのが堅実でしょう。
③ 面談準備を徹底する
銀行との融資面談は、投資家にとって自分を売り込むプレゼンテーションの場です。
成功する人はこの面談準備を徹底的に行い、担当者が「この人になら貸しても大丈夫だ」と思えるような説明をします。
ただ資料を揃えるだけでなく、話す内容や順序まで練り上げて臨む点がポイントです。
5分ピッチの構成(結論→根拠→リスク対策)
面談の冒頭で行う自己紹介や事業計画の説明は、長々と話すより5分程度に簡潔にまとめるのが効果的です。
構成はズバリ「結論→根拠→リスク対策」です。
まず最初に結論として「○○銀行さんから△△万円の融資をいただき、□□市の◇◇という物件を購入・運用したいと考えています」という融資希望の内容を明確に伝えます。
次に根拠として、物件の収支シミュレーションや自身の年収・資産背景、物件の需要予測など「貸しても返済できる」理由を示します。
例えば「この物件は利回り××%で、家賃収入から十分返済可能です。私自身も年収〇〇万円あり、現在他の借入はありません」といった具合です。
最後にリスク対策として、空室が出た場合の予備資金の確保や、火災・地震保険への加入、金利上昇時の対応策(繰上げ返済や固定金利検討)などリスクへの備えを説明します。
結論から入り、数字に基づく根拠を示し、リスク管理も抜かりないことを伝えることで、担当者に与える印象は格段に良くなります。
想定質問と回答例を事前に準備
成功者は、担当者から聞かれそうな質問を事前に洗い出し、その回答を用意して臨んでいます。
例えば「なぜこのエリアの物件を選んだのですか?」「空室が埋まらない場合の対応は?」「金利が上がったら大丈夫ですか?」「本業が忙しい中でどうやって管理しますか?」といった質問が想定されます。
それぞれに対して、自分なりの根拠ある回答を準備しておけば、突然質問されても落ち着いて答えることができます。
逆に準備不足だと、その場で答えに窮して信頼を損なう可能性もあります。
想定問答集を頭に入れておき、どんな質問にも論理的に答えられる状態にしておくことが、「この人は計画性があり信用できる」という評価につながります。
④ 融資に好まれる物件条件を押さえる
融資戦略では「どんな物件を選ぶか」も重要です。銀行が好む物件の条件を理解し、融資が付きやすい物件を選定することで、融資承認の確率を高められます。
不動産投資家の中には「この物件なら銀行ウケが良さそうだ」という視点で物件を吟味している人もいます。以下、銀行に好まれる条件と敬遠されがちな条件を整理します。
好まれる条件(築年・構造・立地)
銀行融資で好まれる物件の特徴として、比較的築浅であること、構造が堅牢であること、そして需要の強い立地であることが挙げられます。
築年数については、築浅であればあるほど法定耐用年数残存期間が長く融資期間を長く取れるため歓迎されます。具体的には木造アパートなら築20年未満、RC造マンションでも築30年未満程度が目安となるでしょう。
また構造面では、耐久性の高い鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨造の物件は評価が高い傾向にあります(木造でも新築なら融資期間を長く取れる場合があります)。
立地については、人口が増えているエリアや駅近物件など賃貸需要が見込める場所が好まれます。都心や主要都市の中心部でなくとも、大学や工場の近隣、交通の便が良い住宅街などは安定収益が期待でき、銀行も前向きに検討しやすいです。
「この物件なら空室リスクが低く、将来にわたり収益が安定する」と銀行に思わせられる物件が理想です。
避けるべき条件(旧耐震・需給弱い立地)
反対に銀行が融資を渋る物件条件も把握しておきましょう。
まず旧耐震物件は敬遠されます。旧耐震基準(1981年以前の基準)で建てられた建物は耐震性で劣り、担保評価が低くなりがちです。大地震時の倒壊リスクなどもあり、銀行によっては旧耐震物件への融資は原則不可としているところもあります。
また、需給バランスが悪い立地、例えば人口減少が著しい地方エリアや、最寄駅から極端に遠い物件、周囲に賃貸需要を生む施設が少ない場所なども要注意です。そういったエリアでは空室率が高くなる懸念があるため、銀行は「収益悪化で返済困難に陥るリスクが高い」と判断します。
極端に利回りが高すぎる物件(いわゆるボロ物件で家賃だけ高めに設定しているようなケース)も警戒されます。
利回りが高すぎる場合、その裏に老朽化や特別な事情による安値物件である可能性があり、長期安定運用に不安があるとみなされるためです。
融資を確実に引きたいなら、物件選定の段階で「銀行目線で問題なさそうか?」を考え、あえて地雷になりそうな条件は避けることが賢明です。
⑤ 長期保有を前提に出口戦略を描く
融資を受けて不動産を購入する以上、長期的な視点での経営計画が求められます。
成功する投資家は「買う前から出口戦略まで描いている」と言われるほど、購入後のシナリオを綿密に考えています。
銀行に融資を打診する際も、短期転売目的ではなく長期保有を基本とした計画を示した方が信頼を得やすいです。ここでは長期保有における資金計画と複数の出口戦略について紹介します。
修繕・保険を見越した資金計画
物件を長期保有する場合、避けて通れないのが修繕費と保険です。
建物は年数が経つほど修繕コストが発生します。成功者は毎月のキャッシュフローから一部を修繕積立金としてプールし、外壁塗装や屋上防水、設備交換など大きな出費に備えています。
また火災保険や地震保険にも適切に加入し、予期せぬ事故・災害による損壊に対する備えも万全にしています。銀行との面談でも「毎月家賃収入の◯%を修繕積立し、突発的な修理にも耐えられる計画です」と説明できれば、長期安定運営への意識が伝わり評価が上がります。
融資返済額だけでギリギリの計画ではなく、余裕を持った資金繰りを計画していることが肝心です。
売却・借り換えなど複数の出口を準備
長期保有を前提としつつも、状況の変化に応じて柔軟に動ける出口戦略を持っておくことも重要です。
成功している投資家は、「最終的には○年後に◯◯万円以上で売却する」「金利が低いうちに◯年後に別の銀行で借り換える」など、複数のシナリオを用意しています。
例えば金利動向によっては固定金利への借り換えや、一部繰上返済を行って返済負担を軽くする作戦も考えられます。
また、マーケットが好調な時期には思い切って物件を売却してキャピタルゲインを確保し、その資金で次のより大きな物件にステップアップするという戦略もあります。
一方で、賃料下落や空室増加など厳しい状況になった場合でも、慌てずに対策できるよう予備資金や別の収入源を持っておくことも出口戦略の一環です。
要は「この物件に一生縛られず、状況に応じて方針転換できる」準備をしておくことが、長期で見たときの安心感につながります。
それが銀行からの信用にもつながり、追加融資や次の物件購入の際にも好印象となるでしょう。
不動産の投資ローンに対応している金融機関

不動産投資家に融資を行っている主な金融機関として、以下の例が挙げられます。
- オリックス銀行
- 静岡銀行
- 香川銀行
- 東日本銀行
- 地銀・信用金庫
上記以外にも、各地域の地方銀行や信用金庫・信用組合が不動産投資ローンを提供しています。
たとえば地方銀行では東京や大阪の物件にも融資可能なところがあり、また信用金庫では地元密着で小規模アパート融資に強いところがあります。
自分の居住地や物件所在地の金融機関を調べ、融資相談に乗ってくれる先を開拓しましょう。特に信用金庫は前述の通り初心者にも門戸が広いので、一行は取引先を作っておくと心強いです。
※金融機関ごとに融資姿勢や条件は年ごとに変化します。最新の金利や融資条件は各行の公式サイトや不動産投資家の口コミなどでチェックしましょう。
よくある質問(FAQ)
年収と自己資金がどれくらいあればいくら借りられる?
不動産投資ローンでいくら借りられるかは物件の収益性やご本人の信用状況によって変わるため一概には言えません
しかし、目安として「年収の約7~10倍」が借入可能額と言われます。
例えば年収500万円で自己資金500万円の方の場合、単純計算では最大5,000万円前後の融資が受けられる可能性があります。
自己資金500万円を頭金として入れれば、6,000万円程度の物件まで手が届く計算です。
ただし実際には、物件から得られる家賃収入やローンの金利・期間などを加味して「返済比率」が適正かどうか審査されます。
年収倍率が高くても家賃収入が充分なら融資承認されるケースもありますし、逆に年収倍率が低めでも他の借入が多いと難しくなることもあります。
銀行は「返済負担率」(年間返済額÷年収)なども見ますので、一般には返済負担率が25~35%程度に収まる範囲で借入額が決定されます。
信金・信組が好む物件の条件は?
信用金庫・信用組合(信金・信組)は、地域密着型で中小規模の融資に積極的です。
そのため「エリア」と「規模感」がポイントになります。
信金・信組の営業地域内にある物件であることが大前提、遠方の物件だと取引自体難しいケースが多いです。
また物件価格・融資額の規模は数千万円程度までの中小物件を好む傾向があります。
1億円超の大型案件より、3,000万~8,000万円くらいのアパート・マンションの方が取り組んでもらいやすいでしょう。
築年や構造については、各信金によりますが築浅~中程度(築20~30年以内)で、木造アパートからRC造マンションまで幅広く対象になります。
ただし旧耐震や空室だらけの物件などリスクが高いものは敬遠されます。借り手側の条件としては、その信金の地域に居住・勤務していることや、預金口座などで取引実績があることが望ましいです。
さらには年収や自己資金がある程度ある(例: 年収400万円以上・自己資金物件価格の1~2割程度)と信用度が増します。まとめると、「地元エリアの適正規模な物件+堅実な属性の借り手」が信金・信組には好まれる案件と言えます。まずは地元の信金支店に相談し、会員(組合員)資格を得た上で関係構築を図ると良いでしょう。
公庫や保証協会付きはいつ使うべき?
日本政策金融公庫(公庫)や信用保証協会付き融資は、主に「民間銀行からの融資が難しい場合の選択肢」として活用されます。
具体的には、以下のケースが利用されるタイミングになります。
- 投資初心者で実績がないとき:公庫は創業融資の延長線上で、小規模な不動産投資にも協力的です。自己資金が少なく民間銀行で断られた場合、公庫なら事業計画次第で融資してくれることがあります。最初の1棟目に公庫を利用し、そこで信用を作って次につなげるという手は有効です。
- 個人属性に不安があるとき:例えば年収が低め・勤続年数が短いなどの場合、保証協会付き融資を検討できます。信用保証協会が保証人となることで銀行のリスクが減り、融資実行されやすくなります。副業で始める大家業の場合や、新設法人で実績がない場合などにも利用されています。
- 大手銀行が消極的な局面で:不動産市況や融資姿勢の変化でメガバンクや一部地銀が融資を渋る時期があります。そんな時、公庫や保証協会枠は比較的安定して融資を提供してくれるので、資金調達の受け皿になります。
注意点として、公庫融資は無担保が基本なので融資金額に上限があります(最近では4,800万円程度が目安)。
保証協会付き融資も保証料負担や保証枠の上限(通常一企業2億8000万円まで等)があるため、事業拡大に従っていずれは直接融資(プロパーローン)へ切り替えることも検討しましょう。
融資に落ち続けたときの対応策は?
融資審査に連続して落ちる場合、どこに原因があるか分析し、対策を講じる必要があります。対応策として次のような点を見直してみましょう。
- 自己資金の増強
- 物件条件の変更
- 金融機関の変更
- 信用情報・属性の改善
- 専門家への相談
落ち続けると心が折れそうになりますが、視点を変えて準備を整えれば道は開けます。
一度立ち止まって戦略を練り直し、再チャレンジしてみてください。
耐震構造や地震保険で意識すべきことはある?
物件安全性の観点から、旧耐震(1981年基準以前)は原則避ける/新耐震基準を基本とします。
ただし新耐震でも被害が出る可能性はゼロではありません。
築古・長期保有は地震保険の活用を基本にしつつ、保険金上限(例:5,000万円)を踏まえてLTVや現金クッションで備えます。築浅や短期売却見込みでは加入を見送る判断をするケースもあります。
まとめ
不動産投資において「融資戦略」は物件選び以上に重要な要素であり、成功する投資家は皆ここに注力しています。
融資の基礎知識を押さえ、自分の年収・資産規模に合った資金計画を立てることで、無理なく物件を増やしていくことができます。
特に初心者のサラリーマン投資家の場合、自己資金を着実に貯め、地元の信用金庫など身近な金融機関から実績を積み上げるのがおすすめのルートです。
面談対策や物件選定の工夫によって融資のハードルを下げることも可能です。また、一つひとつの物件を長期安定運用する視点を持ち、出口戦略まで描いておくことで、銀行からの信頼も得られやすくなります。
ぜひ本記事で紹介したポイントを踏まえ、融資戦略を磨いて不動産投資の成功確率を高めてください。
なお、今回の内容は動画でも解説しています。文章よりも動画で内容を確認したい方は、こちらをご覧ください。
”元ゴールドマン・サックス不動産投資家が教える失敗しない不動産投資の成功法則”を
LINE友だち限定でお伝えします。
LINE登録でもらえる豪華6大特典
①数字とエビデンスに基づく投資判断マニュアル
②自分に最適な「融資」を見つけるガイド
③不動産購入前に必ず確認すべき「リスク」と「資料」
④ 「お宝物件」発掘のための効果的な探し方
⑤『不動産購入「現地調査」で確認すべきチェックリスト
⑥不動産運営にかかる収益費用の把握の仕方
LINE友だち追加してくれた方だけに、登録者6万人のYouTubeでも話せない情報をお届けしています
小原正徳の公式LINEはこちらから
▼スマホはこちらから限定情報をGET!▼
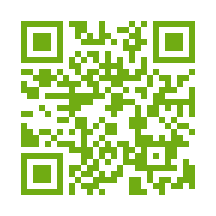

【監修者情報】不動産投資家 小原 正徳
1981年4月6日生まれ 不動産投資家
東京大学卒業後、EYグループ不動産部門、
ゴールドマン・サックスグループ不動産ファンド部門を経て
2016年に東京都新宿区株式会社不動産科学研究所で独立
2022年には総資産20億円を形成
同年、新たなチャレンジとして不動産投資スクールを開校し、自身の培ったノウハウの提供を開始
株式会社不動産科学研究所 代表取締役
宅地建物取引士
不動産鑑定士
不動産証券化協会認定マスター









