不動産投資における減価償却の活用は、高額な税負担に悩む法人経営者や高所得サラリーマンにとって、有効な節税戦略です。
収益物件の運用で生じた会計上の赤字を本業の給与所得と損益通算し、課税所得を圧縮できるからです。
特に減価償却費は「支出を伴わない経費」であり、現金の流出なしに税負担を軽減できる点が大きな魅力です。
本記事では、この減価償却を活用した節税の仕組みと効果、具体例、さらに活用時の注意点について解説します。
”元ゴールドマン・サックス不動産投資家が教える失敗しない不動産投資の成功法則”を
LINE友だち限定でお伝えします。
LINE登録でもらえる豪華6大特典
①数字とエビデンスに基づく投資判断マニュアル
②自分に最適な「融資」を見つけるガイド
③不動産購入前に必ず確認すべき「リスク」と「資料」
④ 「お宝物件」発掘のための効果的な探し方
⑤『不動産購入「現地調査」で確認すべきチェックリスト
⑥不動産運営にかかる収益費用の把握の仕方
LINE友だち追加してくれた方だけに、登録者6万人のYouTubeでも話せない情報をお届けしています
小原正徳の公式LINEはこちらから
▼スマホはこちらから限定情報をGET!▼
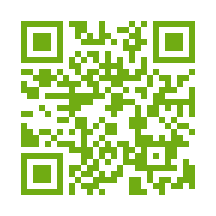

【監修者情報】不動産投資家 小原 正徳
1981年4月6日生まれ 不動産投資家
東京大学卒業後、EYグループ不動産部門、
ゴールドマン・サックスグループ不動産ファンド部門を経て
2016年に東京都新宿区株式会社不動産科学研究所で独立
2022年には総資産20億円を形成
同年、新たなチャレンジとして不動産投資スクールを開校し、自身の培ったノウハウの提供を開始
株式会社不動産科学研究所 代表取締役
宅地建物取引士
不動産鑑定士
不動産証券化協会認定マスター
不動産投資における「減価償却」とは?

不動産投資で減価償却費を活用した節税とは、物件購入時に支払った建物価格を毎年少しずつ経費計上し、その分だけ所得を圧縮して納税額を減らす手法です。
そもそも減価償却とは、時間の経過とともに価値が下がる建物や設備の購入費用を、支出した際に一度に全額経費にせず法定耐用年数に沿って数年に分けて費用計上する仕組みです。
物件の価格は土地と建物の価格に分かれますが、土地は減価償却できないため、建物部分の価格のみが毎年経費化されます。
建物価格を計画的に減価償却として計上することで、その分だけ所得(利益)を減らせるため、結果として課税所得を抑えることができます。
例えば1億円で購入した物件(うち建物価値5000万円)を耐用年数25年で減価償却する場合、毎年約200万円を経費計上できます。
これにより毎年200万円分だけ所得が減少し、その分の所得税・住民税が軽減されます。仮に税率が合計40%であれば、年間約80万円の税負担軽減効果が得られる計算です。
このように、不動産投資では減価償却費を計上して所得を引き下げることで、大きな節税効果を生み出すことが可能なのです。
減価償却の仕組みと対象範囲
不動産投資における減価償却とは「建物や設備の価値を耐用年数に応じて分割して経費計上する仕組み」であり、土地だけでは対象外になります。理由は、時間の経過で劣化する資産だけが経費として扱われるためです。
建物は年月とともに劣化しながら賃料収入を生み出すため、費用も同じ期間に割り振るべきという「費用収益対応の原則」に基づき、減価償却が行われます。
一方、土地は劣化せず価値が減少するものではないとみなされるため、償却対象外とされているのです。
例えば、1億円で購入した物件が「土地6,000万円、建物4,000万円」と評価された場合、減価償却できるのは建物部分の4,000万円のみです。
また、建物に付随する設備(エレベーターや空調、給排水設備など)も耐用年数が定められており、建物本体とは別に減価償却できます。これにより、経費計上を柔軟に行える点が投資戦略上のポイントになります。
減価償却の計算方法
減価償却の計算方法は「建物価格 ÷ 耐用年数」で年間の償却費を算出します。ここで重要なのは、どの耐用年数を適用するかという点です。
耐用年数は税法で定められており、建物の構造や用途によって異なるからです。
例えば、木造住宅は22年、鉄筋コンクリート造の住宅は47年と定められており、構造が堅牢なほど耐用年数は長くなります。
このルールに基づき、毎年一定額を経費として計上できるのです。
例えば、建物価格が4,000万円で耐用年数が47年の鉄筋コンクリート造マンションの場合、1年間の減価償却費は「4,000万円 ÷ 47年 ≒ 約85万円」となります。
つまり、実際には現金の支出を伴わずに、毎年85万円を経費にできるという大きなメリットがあります。中古物件であれば耐用年数を短縮して計算できる特例もあり、節税効果をさらに高められるケースもあります。
不動産投資の減価償却が「節税」につながる理由

不動産投資において減価償却費が節税手段となる主な理由は、大きく2つあります。以下でそれぞれ詳しく解説します。
減価償却費は支出を伴わないので手取り自体が増える
減価償却費は実際の支出を伴わない経費であるため、同額の他の経費を計上する場合に比べて手元資金を減らさずに税負担を軽減できます。
通常、経費を計上すれば利益が減って納税額も少なくなりますが、多くの経費(例:接待交際費や修繕費など)は支出を伴うため、節税してもその分だけ現金が出ていきます。
一方、減価償却費は帳簿上で費用計上して利益・税額を圧縮できるにもかかわらず、当期における現金の支払いは伴いません。
つまり、減価償却費を計上すれば、その分だけ税金が減り、その額の分そのまま手元資金が増加するのです。
減価償却費のように「支出を伴わない経費」は、節税額イコール手元資金のプラスに直結するため、非常に有効な節税手段となります。
損益通算で個人所得の黒字と赤字を相殺できる
減価償却によって不動産所得が赤字になった場合、その赤字分を給与所得など他の所得と損益通算できるため、個人全体の課税所得を大きく圧縮できます。
日本の所得税は総合課税方式であり、不動産投資で生じた損失(赤字)は給与所得など他の所得の黒字と相殺することが可能です。
特に高所得者の場合、本業の給与や事業所得から減価償却による赤字分を差し引くことで、課税対象となる所得金額を大幅に減らすことができます。
その結果、高い累進税率が適用されていた部分の所得が減るため、節税効果が顕著に現れます。
例えば、年収1200万円のサラリーマンが不動産投資で減価償却費を計上し、年間500万円の不動産所得の赤字を作り出したとしてシュミレーションします。
損益通算によってこの500万円の赤字を給与所得から差し引くと、課税上の所得は実質年収700万円程度とみなされ、納める税金は大幅に減少します。
結果として、本来1200万円の所得にかかるはずだった税金が圧縮され、手元に残るお金が増えるのです。
このように、減価償却による不動産の赤字は高所得者の給与所得などと相殺することで強力な節税効果を発揮し、全体の税負担を軽減します。
不動産投資で減価償却を活用して節税を行う際のリスク

不動産投資で減価償却を活用して節税を目指す場合、以下の2つの点に注意しましょう。
- 節税効果が限定的なケース
- 税引後キャッシュフローの悪化リスク
それでは詳しく解説します。
節税効果が限定的なケース
減価償却を利用した節税は万能ではなく、物件の条件によって効果が限定的になる場合があります。
特に「高値掴みをした物件」や「土地割合が大きすぎる物件」では注意が必要です。
購入価格に占める土地の割合が大きいと、減価償却できる建物部分が相対的に小さくなるため、経費計上の幅が狭まるからです。
また、相場より割高に購入した場合、実際の収益性に対して減価償却の節税効果が薄く感じられることもあります。
例えば、同じ1億円の投資でも、土地が8,000万円・建物が2,000万円という物件では、建物部分の償却額は小さく、節税効果は限られます。
逆に、土地と建物が5:5のバランスであれば、償却費を多く計上できるので節税効果も大きくなります。
物件選びの段階から「建物割合の大きさ」や「購入価格の妥当性」を確認することが重要です。減価償却に着目するあまりに、割高な価格で物件を買ってしまってはかえって資産を減らすことになります。
税引後キャッシュフローの悪化リスク
減価償却によって節税効果が出ても、税引後のキャッシュフローが悪化するリスクがあります。
減価償却費は「お金が出ていかない経費」である一方、実際の融資返済(元金部分)は経費にならないためです。このズレによって、帳簿上は黒字でも手元資金が不足する「逆ザヤ状態」に陥るケースがあります。
年間家賃収入が1,000万円、減価償却費が300万円ある場合、帳簿上の利益は圧縮され税金は減ります。
しかし、ローン元金返済が毎年500万円あると、経費にできない支出が大きいため、実際にはキャッシュフローが赤字になる可能性があります。
つまり、減価償却の節税効果だけに目を奪われると、資金繰りを誤る危険があるのです。
節税を狙う際は、必ず「税引後キャッシュフロー」でシミュレーションを行い、返済負担とバランスを取ることが不可欠です。
私自身は、減価償却期間とローンの元金返済期間ができるだけ一致するように、物件の取得や融資設計を行っています。そうすることで、帳簿上の利益と実際の資金の動きが大きく乖離せず、無理な調整をせずとも税引後キャッシュフローが安定しやすくなるからです。
初心者のうちは特に、利益が出ているのに手元資金が不足する「逆ザヤ」状態を避けるためにも、このようなバランス設計をひとつの参考にしてみてください。
不動産投資の減価償却で節税を最大化するポイント

減価償却を活用して節税効果を最大化するためにはちょっとしたポイントがあります。
減価償却をうまく活用して資産を残せるよう、以下のポイントを確認しておきましょう。
建物割合を大きく設定する
契約時に建物割合を適切に設定することで、減価償却額を増やし節税効果を高められます。
なぜなら土地は減価償却の対象外である一方、建物部分は経費化できるからです。
同じ購入金額でも「土地7割・建物3割」と「土地5割・建物5割」では、後者の方が減価償却で計上できる額が多くなります。
もちろん根拠のない割合は認められませんが、固定資産税評価額や不動産鑑定士の評価を参考に、建物割合を現実的に高める工夫は可能です。
設備と建物を分ける
建物と設備を分けて計上することで、短期的に大きな減価償却を行える可能性があります。
建物の耐用年数は長期(木造22年、RC造47年など)に設定されていますが、設備は10〜15年程度と短いため、より早く経費にできるからです。
例えば、空調設備や給排水設備、エレベーターなどは建物とは別に計上可能です。
建物全体で4,000万円のうち、空調設備500万円を15年で償却できるとすると、年間約33万円を追加で経費化できます。
建物全体を含めて47年で割るよりも早期に償却できるため、初期の節税効果を高められます。
中古物件は耐用年数を短縮できる
中古物件を購入すれば、法定耐用年数を短縮して計算でき、早期に減価償却を進めることが可能です。
税法で「中古資産は残存耐用年数を簡便法で算出できる」と定められており、新築と比べると耐用年数を短く設定できるので、より早い節税効果が期待できます。
例えば、築20年の木造アパート(法定耐用年数22年)を購入した場合、「耐用年数=法定年数−経過年数+経過年数×20%」という計算式で残存耐用年数を算出します。
このケースでは残りわずか4年程度となり、数年間で一気に経費化できるのです。短期間に減価償却を集中させられるため、所得税や住民税の負担を大きく軽減できます。
つまり、中古物件を選ぶことで、節税効果を早期に享受できるだけでなく、キャッシュフロー改善にもつながるのです。
融資や決算を重視する場合は減価償却を小さくする戦略も有効
節税よりも決算額で収支を増やしたり、融資でプラスに働くように調整したい場合は、減価償却を小さくする戦略も有効になります。
節税効果は減りますが、帳簿上の利益を厚く見せることで金融機関や投資家からの信頼を高められます。
金融機関が融資判断の際に重視するのは「返済能力=利益水準」です。減価償却を大きく取りすぎると経費が膨らみ、帳簿上の利益が少なくなります。節税効果は得られるものの、利益が小さいことで「資金余力が少ない」と判断され、融資枠が制限されるリスクがあるのです。
逆に、減価償却を抑えて利益を多く見せれば、決算書の評価が高まり、より有利な条件で融資を受けられる可能性があります。ここからは、具体的に「減価償却を小さくする戦略」を紹介します。
建物割合を小さくする
購入時に建物割合を小さく設定すると、帳簿上の利益を厚く見せられ、融資審査を有利に進められる可能性があります。
建物部分が小さいほど減価償却額が減少し、経費が少なくなるため利益が多く計上されるからです。
金融機関は融資判断の際に「利益の安定性」や「返済能力」を重視するため、黒字を大きく見せることは信用力につながります。
同じ1億円の物件を購入した場合、土地6,000万円・建物4,000万円としたケースでは年間償却額が約85万円になります。
一方、土地7,000万円・建物3,000万円と設定すれば、年間償却額は約64万円に減少し、その分利益が増えます。結果として決算書の数字が改善し、金融機関の融資評価でプラスに働くのです。
このため、節税よりも資金調達を重視する場面では、建物割合を意識的に抑えることが一つの有効な戦略となります。
耐用年数を長く設定する
耐用年数を長めに設定することで、利益を安定的に見せる効果があり、金融機関への印象を良くできます。
耐用年数を長くすると1年あたりの減価償却費が小さくなり、利益がブレにくくなるからです。
金融機関は短期的な赤字よりも、長期的に安定した黒字を評価する傾向があるため、決算書の数字を「安定的に黒字」に保つことが重要です。
例えば、建物3,000万円を耐用年数30年で償却すると年間100万円の経費になりますが、50年で償却すると年間60万円に抑えられます。
結果として利益額が増え、長期的に安定した経営基盤を示すことが可能になります。ただし、金融機関から「利益操作」と見なされるリスクがあるため、根拠のある設定を行うことが前提です。
つまり、耐用年数を長めに設定する戦略は、あくまで金融機関の信頼を獲得するための補助的な方法であり、バランス感覚を持って活用することが求められます。
まとめ
不動産投資における減価償却は、高年収のサラリーマンや法人にとって「節税」と「資金戦略」を両立させる強力なツールとなります。
減価償却をうまく活用すれば、税負担を軽減しながら手元資金を残し、さらなる投資拡大の原動力に繋げられます。
建物割合を調整したり、設備を建物と分けたり、中古物件の耐用年数短縮を活用することで、節税効果を高められます。
一方で、融資や決算を重視する場合には、あえて減価償却を小さく設定し、帳簿上の利益を厚く見せる戦略も有効です。
このように、減価償却は「増やす・減らす」のどちらも投資戦略に直結するのが特徴です。
不動産投資における減価償却は万能ではありませんが、正しい知識と戦略で活用すれば、長期的に「お金を残す力」を高められます。
節税と融資のバランスを見極め、税理士などの専門家の助言を得ながら、自分の投資目的に合った方法で実践することが成功の鍵です。
”元ゴールドマン・サックス不動産投資家が教える失敗しない不動産投資の成功法則”を
LINE友だち限定でお伝えします。
LINE登録でもらえる豪華6大特典
①数字とエビデンスに基づく投資判断マニュアル
②自分に最適な「融資」を見つけるガイド
③不動産購入前に必ず確認すべき「リスク」と「資料」
④ 「お宝物件」発掘のための効果的な探し方
⑤『不動産購入「現地調査」で確認すべきチェックリスト
⑥不動産運営にかかる収益費用の把握の仕方
LINE友だち追加してくれた方だけに、登録者6万人のYouTubeでも話せない情報をお届けしています
小原正徳の公式LINEはこちらから
▼スマホはこちらから限定情報をGET!▼
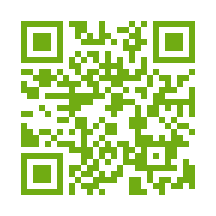

【監修者情報】不動産投資家 小原 正徳
1981年4月6日生まれ 不動産投資家
東京大学卒業後、EYグループ不動産部門、
ゴールドマン・サックスグループ不動産ファンド部門を経て
2016年に東京都新宿区株式会社不動産科学研究所で独立
2022年には総資産20億円を形成
同年、新たなチャレンジとして不動産投資スクールを開校し、自身の培ったノウハウの提供を開始
株式会社不動産科学研究所 代表取締役
宅地建物取引士
不動産鑑定士
不動産証券化協会認定マスター









